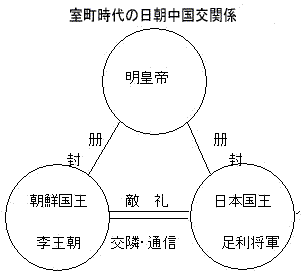
江戸時代の朝鮮および中国との国交関係は、これを歴史的に言えば、足利義満がはじめた室町時代の国交関係を基礎に、それを修正したものとみなせる。それを模式化すれば、次の「室町時代の日朝中国交関係」のようになるだろう(じつはこの図は完全なものとは言えない。このことは後述する)。
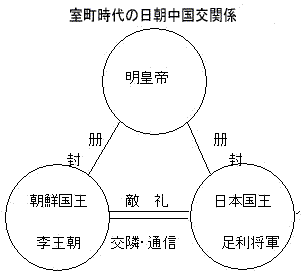
日本と朝鮮の双方の君主(=対外的主権者)が明王朝の皇帝と直接に朝貢関係をもち、皇帝から日本国王、朝鮮国王に任命された上で、両者が独自に国交を取り結んでいる。両者の国際的な対等性(「敵礼」)はともに中国の皇帝との関係によって保証されていることになる。これがノーマルな形での「交隣関係」であり、この関係は前近代東アジア世界の国際秩序である「中華帝国体制」に完全に組込まれたものとして実存していた。東アジア世界レベルの国際ルールと矛盾する点は少しもなかった。
ところが、江戸時代日本の対外的主権者である徳川将軍と明清両王朝の皇帝との間に朝貢関係がつくられたことは一度もなかった。だから、上記の意味での「交隣関係」はそもそも成立しようがない。そのこともあって、一時期の例外をのぞいて、将軍は対外的には「日本国王」の称号を用いなかった。にもかかわらず、「日本国大君」すなわち将軍と朝鮮国王との間に外交上の対等性(「敵礼」)は維持されえたのである。そのことは両者の間で交わされた国書の書式の対称性が雄弁に物語っている。もちろん、この朝鮮国王と日本国大君の対等性が保証されなければ、安定した日朝関係の長期にわたる継続は望むべくもなかったであろう。
どうしてそのようなことが可能だったのか。一つの理由としては、朝鮮側が、中国皇帝から承認された正式な日本国王でなくとも、実質的な日本の君主(すなわち日本国大君)として徳川将軍を受け入れたことがあげられよう。その背景には壬辰・丁酉倭乱の後始末とその再発防止という朝鮮側の安全保障上の国家戦略があったと考えられる。
第二に、日本、中国双方において、日中間に正式の国交関係が成立していなくとも、大きな困難は生じないとの認識が成立し、しかも長期間にわたりそれが保持できた環境ないし条件が存在していたことも重要であろう。具体的には、徳川幕府による全国統一と、それに踵を接して生起した、明清の王朝交代とそれにともなう東アジアの政治的大変動および国際秩序の再編、その動きを背景とする日中双方での海禁と互市の併用政策、さらには日本の内国経済の自給自足性の高まり、などといった一連の要因が考えられよう。
さらに第三には、日本国内の政治的事情として、将軍職が天皇から征夷大将軍に任命されるものであり、将軍が形式的には自分よりも上級の君主を有していた事実を看過すべきではない。その結果国際的に、中国皇帝を上級君主とあおぐ朝鮮国王と将軍との間に、平行関係(「敵礼」)を形成しうる余地が生じたからである。それを示す図が次の「江戸時代の日朝中国交関係」である。
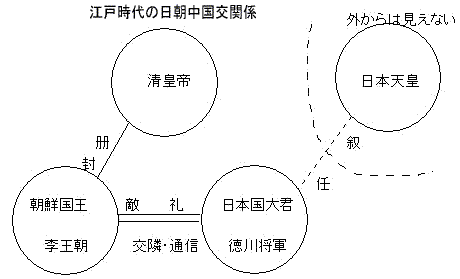
あらためて言うまでもないが、幕末になって朝廷・幕府間の権力関係が変動するまでは、江戸時代の天皇は対外的には日本を代表する存在でなかった。外交権の保持者は将軍であり、天皇はそれとは無縁であった。国際関係上は、外から見えない状態に天皇は置かれていたのである。このように、天皇が外からは見えないところで、将軍の名目的上級君主であったことが、室町時代の関係が完全に復活したわけでないにもかかわらず、朝鮮国王と日本国大君の対等性を可能にし、日朝間の「交隣関係」をうまく機能させた要因となったのではないだろうか。
この点について、もう少し説明したい。そもそも日朝中関係はこうあるべきだと主張する外交理念としては、上記のような室町時代の「足利義満モデル」とは異質なモデルが、それ以前から日本には存在していた。それを模式化したのが次の「古代律令制的対外理念における日朝中関係」である。
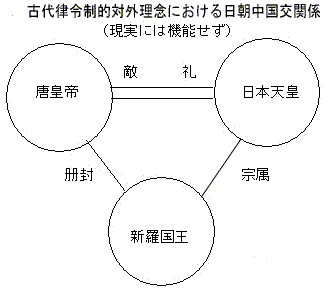
ここに図式化したのは、日本の天皇と中国の皇帝とは対等な関係にあるとし、その上で新羅=朝鮮は日本に服属すべき存在であると考える対外理念である。公式令の規定、「蕃(=藩)国は新羅、隣国は唐」はその外交理念の表明であり、聖徳太子が遣隋使にもたせたと言われる国書(「日出処の天子書を日没する処の天子に致す云々」もまた、この観念の産物であると言ってよい。
もちろん、これはあくまでも日本の古代国家の抱いていた対外理念なり目標であって、このような関係が現実のものとして実在したかどうかは、自ずから別問題である。歴史的には、一度も実現されなかったとみるべきであろう。
このような対外理念が主張されるかぎり、中華世界の中心にある皇帝との関係がうまくいくはずはないし、朝鮮との「交隣関係」など原理的に成立不可能であろう。「足利義満モデル」が前近代東アジア世界の国際秩序であった「中華帝国体制」と調和的、というよりその体制の構成要素そのものであったのに対して、このような対外理念はそれとは相容れない関係にあり、敵対的な性格をもつものと言わざるをえない。
だから、もしも、この対外理念が積極的に主張され、それに合致するように対外関係を構築しなおそうとして、日本が対外行動に打って出れば、外交紛争は不可避であり、国交の断絶からさらに進んで戦争へと事態の展開は避けられなかったにちがいない。日本の天皇を中国の皇帝の地位につけようと考えた豊臣秀吉の対外行動は、まさにその実例と言えよう。実際、中国を完全に征服して天皇自らがその皇帝とならなければ、上記の観念の現実化は不可能だからである。
このように、対外的摩擦を引き起さずにはおかない対外理念であるために、それを対外行動の積極的指針とすることには多くの困難がともなう。その困難を前にして、現実的達成をあきらめ、東アジア世界のグローバルな国際ルールに順応すべく、そのような対外理念そのものを放棄あるいは現実的な妥協(たとえば遣唐使のように)を行うか、そうでなければ、逆に東アジア世界内での他者との関係の構築そのものを避ける(遣唐使の廃止後平氏政権の登場まで)ことで、消極的ながらも対外理念の防衛と保持をはかるか、いずれかを選択することになるだろうと考えられる。しかしながら、現実的な解としては、じつはもう一つの道があったのである。
先にあげた「江戸時代の日朝中関係」の模式図は、いずれも三項関係である「足利義満モデル」と「古代律令制的対外理念」とはちがって、四つの頂点を含んだ四項関係図になっている。そのことは、この関係が単一のものではなくて、二つの異なる三項関係を連結させた複合的なものであることを意味する。すなわち「江戸時代の日朝中関係」は、対外的には室町時代の「足利義満モデル」を継承しつつも、同時に対内的には「古代律令制的対外理念」を、形をかえつつ保存しているとみることができるのである。
徳川将軍と朝鮮国王が現実の国際関係において対等であるがゆえに、観念的には、それぞれの上級君主である中国皇帝と日本天皇とは対等な関係に置かれることになる。逆に中国皇帝と日本天皇が理念的には対等な存在であるがゆえに、徳川将軍と朝鮮国王とは対等な立場で国交を結ぶことができる。その意味で、「江戸時代の日朝中関係」は「足利義満モデル」と「古代律令制的対外理念」との折衷モデルであると位置づけられよう。
そのような関係が、ほぼ200年にわたって安定的に維持・継続できたのは、言うまでもなく、第四項をなす日本の天皇が終始一貫、東アジアの国際社会において、対外的には見えない存在でありつづけたからにほかならない。はなはだ逆説的ではあるが、日本の天皇は、対外主権を臣下である将軍に譲渡し、自らは国際社会から見えない存在として後ろに退がるのと引き替えに、古代律令制的対外理念を全面的に放棄する事態に追い込まれるのを回避しえたのであった。もちろん、天皇が対外主権を保持しない以上、それを「対外」理念と呼ぶのは概念の不当な拡張かもしれないが、しかし将軍と天皇の関係性の中にその理念の尻尾が残っていたのは否定しえない事実である。
逆に将軍は、対外主権を保持しながらも、国内的には形式的上級君主としての天皇を残存させることで、自らは「古代的律令制的対外理念」の担い手となるのを免れることができた。将軍が天皇に代って、日本の君主として中国皇帝との対等性を主張すれば、彼は東アジアの国際社会で安定的な国際関係を築くことはできない。しかし、国内的には天皇の臣下であるとの位置づけを受入れさえすれば、将軍が朝鮮国王と対等な国交関係を取り結んでも(それは理念的には中国皇帝への対外的「臣従」を内包する)、「古代律令制的対外理念」に抵触するとの非難は最小限に抑えられるのである。つまり、このシステムによってはじめて、「古代律令制的対外理念」を縮退したかたちであれ保持しつつも、同時に伝統的な東アジア国際社会のルールに順応した安定的国交関係を構築することが可能となったのである。言葉を換えれば、日本は天皇と将軍との二重君主制を採用することによって、東アジアの伝統的国際社会の調和的メンバーとなりえたのであった。
ところで、ここで分析した江戸時代の日朝中国交関係を支えていた日本側の国内条件、すなわち
(1)天皇は対外主権を将軍に譲渡し、自らは対外的に見えない存在に退いている。
(2)将軍は対外主権の保持者として外交権を保持するが、しかし名目的上級君主として天皇を戴いている。
の二条件は、基本的には室町時代にも存在していたと見るべきであろう(ただし、足利義満その人は将軍職を子の義持に譲ったあとに日本国王となった)。
だとすれば、最初にあげた「足利義満モデル」はじつは室町時代の日朝中関係を示す模式図としては、未だ完全なものとは言えないことになる。すでに室町時代においても江戸時代のような四項関係は成立しており、それゆえ最初にあげた図は次のように修正されなければならないだろう。
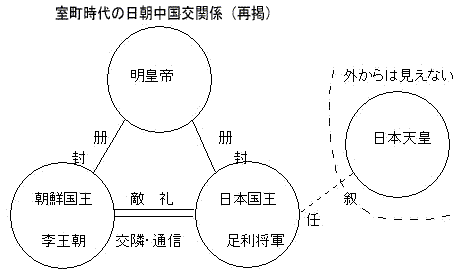
以上の考察を前提にすれば、逆に天皇が外から見える存在に転化した時、言い換えれば、日本の君主として対外的にも日本を代表する存在となった時、その対外理念が古代律令制的なもののままであれば、日本の対外行動が東アジアの伝統的な国際秩序である中華帝国体制や日朝の交隣関係と矛盾し、不適合をおこすのは半ば必然的であったと言わねばなるまい。実際、そのような不適合に由来する紛争が明治維新後ただちに日朝関係において生じたのは、よく知られた事実である。
明治元年12月すなわち王政復古の大号令が出されてから約1年後に、対馬藩の藩主は新政府の命を受けて朝鮮に使節を派遣したが、その大修大差使がもたらした、明治政府の成立を通告する書契が朝鮮側に引き起こした反発は、聖徳太子の国書なるものが隋の朝廷に与えたのと本質的には同じものと言えよう。
日朝合意のもとに積み上げてきた「交隣関係」の外交ルールに違反するとして朝鮮側が問題にしたのは、すべて天皇がらみの字句(「皇上」「登極」「万機親裁」「左近衛少将」「朝臣」)であった。朝鮮側としてはこれは受け入れがたい文字である。なぜなら、言うまでもないが、日本の天皇がこの種の文字を使用するのを容認することは、中国皇帝と日本天皇の対等性を承認することであり、それは朝鮮国王よりも上位の存在として日本の天皇があることを朝鮮側が認めるに等しいからである。そして、それは日本国大君と朝鮮国王の対等性の上に維持されてきた17世紀以来いや遡れば15世紀以来の「交隣関係」に終止符を打つことにつながる。
そのことは対馬藩側にもよく認識されており、外交文書の形式が400年の歴史を有する日朝間の外交ルールに違反することは百も承知の上で、敢えて実行されたのだった。使節派遣に際して、対馬藩主が「新方式の導入は従来の方式を一新し、対馬藩と朝鮮王府の間に維持されてきた外交関係を破棄するに等しいことなので、対馬との関係断絶、貿易停止の措置をもって朝鮮側がこれに報いるやもしれぬ。たとえそうなっても、藩内一同一致協力して難局に立ち向かい、あくまでも初志貫徹につとめるように」との趣旨の布告を領内に出したことからも、それは明らかであろう。
この「大修大差使書契」の受理をめぐって生じた外交上のトラブルは、伝統的な東アジアの国際社会を支えてきた外交理念と、それとは敵対的な日本の古代律令制的外交理念との衝突にほかならない。歴史的にその根は深く、前近代であれば、この外交トラブルを起点として、日本側は先に述べたような対外方針選択の岐路に立たされ、ループを再び描くことになったであろうと思われる。
しかし、時すでに近代に入った東アジアの国際状況は大きく変容しつつあった。そのために、その後の事態の展開は前近代とはまったく異なる方向に進んだのである。アヘン戦争以降、中華帝国体制の一元性は破壊され、東アジア世界の国際秩序は、それとは異なる原理に律された、より大きな別の国際秩序(=近代国際社会)によって包摂されつつあった。その過程で伝統的な東アジアの華夷秩序原理は相対化にさらされ、それにともなって「古代律令制的対外理念」と伝統的な東アジアの国際ルールとの間の衝突の織りなすドラマは従来とはまったく異なった環境のもとで演じられることになった。
同じ明治政府の成立通告であっても、西洋列強との外交関係においては、この種のトラブル・不整合は生じなかった。日本の天皇が外交文書でいくら「皇帝」(Emperor)と自称しても、それが外交ルールに違反するなどとは解釈されなかった。古代ローマあるいは中世ヨーロッパであればまた話は別だが、「主権国家の至上性」なる観念が成立し、それが国際社会を律する近代的原理として定立されて以降、西洋諸国を中心に形成された近代国際社会においては、国際社会を構成する主権国家は、それ自体至高のものとして原理的に相互対等であり、一国の君主が皇帝(Emperor)と名のろうが、国王(King)と名のろうが、それが主権国家の代表であるかぎりにおいてすべては同列であって、そこに原理的に優劣の関係はない。主権者が対外的にどのような称号を名のるかは主権国家の自由勝手であって、それだけでは何ら他の主権国家を拘束するものではない、との解釈が定着していたからである。
日本の「古代律令制的対外理念」はその出自において、近代国際社会を律する原理とは無縁であった。しかしながら、日本天皇は中国皇帝と対等であるとするその一点において、諸国家・諸民族を超越する、唯一の普遍的統合者としての「皇帝」という世界理念を容易に放棄できない中国や朝鮮に比べて、新たに外からもたらされた近代的な国際関係の原理に対してより親和的であり、それゆえにいち早くそれに順応することができた。しかもこの近代国際法原理(「万国公法」)は、前近代には単なる観念にとどまっていた「古代律令制的対外理念」を、かたちを変えてではあるが、はじめて達成可能なものとしてよみがえらせたのである。
外から見えなかった天皇が国際場裡に姿を現してから四十数年後、「大修大差使書契」をめぐる外交トラブルに端を発した近代の日朝関係は、朝鮮の「独立」(伝統的中朝関係の切断)を経て、韓国の保護国化と日本による併合というかたちで結局をむかえた。その時、明治天皇は旧朝鮮国王の末裔である韓国皇帝を李王に封じたのである。近代国際法原理に依拠して進められた朝鮮の植民地化の過程の最後に、「古代律令制的対外理念」があたかも「だまし絵」のようにして浮かび上がってくるのを見てとることができる。
近代国際法原理に自らの身を委ねることによって、前近代にはおよそ不可能であった日本の古代的な対外理念が、前近代とは異なる姿で実現された時代、それが東アジアの「近代」であった。
21世紀COEプロジェクト「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」『東アジアにおける国際秩序と交流の歴史的研究』NewsLetter no.2、2004に掲載。