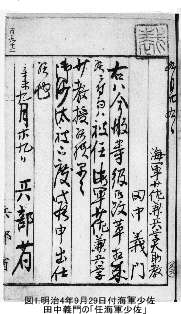
注記:2004年9月17日に、ソウル大学校国際学大学院日本研究センターでおこなった特別講義の原稿である。
この報告は、永井和「万機親裁体制の成立―明治天皇はいつから近代の天皇となったか」『思想』557、2004年をもとにしており、それに若干の補足をおこなったものである。
はじめまして。永井 和と申します。日本の京都大学で日本の近現代史を教えています。私の講義を聞きにきて下さったことに対して、まずお礼を申し上げます。このソウル大学校で、自分の研究の成果を披露できる機会を与えられたことは、まことに身に余る光栄であり、お招きいただいた金容徳(キム・ヨンドック)先生をはじめとする、国際学大学院および日本研究センターの皆様に、あつくお礼申し上げます。
本題に入ります前に、皆様のご理解を得たいことがあります。お恥ずかしい話ですが、私は日本語以外の言語を喋ることができません。今日の講義も日本語で行いますが、まずその点をお許し願いたく思います。と言いますのは、ソウルに出発する前に、私の恩師である京都大学名誉教授の松尾尊輀先生から、次のような教えを受けたからです。
松尾先生は、今から15年ほど前にソウル大学校で講演されたことがあります。その時のことは、先生が最近刊行されました『昨日の風景』(岩波書店)に収録されている「訪問記」に詳しく記されていますが、私がソウル大学校に招かれたことを先生に告げますと、こう言われました。
韓国へ行ったら、通じるのが当然のように思って、日本語を話してはいけない。日本語を使ってもよいことがはっきりしている場合以外では、できるかぎり日本語を使わないようにすべきである。私(松尾先生のことです)が韓国を訪問した時には、ホテルなどではすべて英語でとおしました。
松尾先生は、日本の近現代史を専攻する日本人の研究者の心構えを説かれたのですが、それは先生がアメリカのハーバード大学に留学された折に、親しくなられた、韓国から留学されている学者の方々との交流から、身をもって学ばれたものでした。先ほど紹介したご本には、その時の経験から「反日こそ真の意味での親日である」との思いを深めたと記されてあります。
その教えを胸に、こちらに参りましたが、何しろ私は、韓国語はもちろん、松尾先生とはちがって英語の会話すらままならぬ身ですので、なかなかうまくいきません。ただ、今日のこの講義は他ならぬ日本研究センターで行われますので、ここならば日本語で話をしても、恩師の教えに背いたことにはならぬだろうと、安心しております。
前置きはこのくらいにして、本題に入らせていただきます。
東京の独立行政法人国立公文書館のWebサイト( http://www.archives.go.jp/list/kichou.html)にアクセスすると、同館が所蔵している貴重資料が画像つきで電子展示されているのを見ることができる。そのひとつに「徳教に関する勅語の件」と題された「公文類聚」所収の内閣文書(1)がある(http://www.archives.go.jp/list/kichou_104.html#)。
「徳教に関する勅語」とはいわゆる教育勅語のことだが、掲示されているのは教育勅語の本体そのものではなくて、明治23(1890)年10月20日の日付をもち、内閣総理大臣伯爵山県有朋の記名と花押のある一枚の公文書である。鳥ノ子紙の内閣罫紙に「徳教ニ関スル勅語ノ件 右謹テ裁可ヲ仰ク」と記されただけの簡単なものだが、文面が示すように、教育勅語の制定につき明治天皇の裁可を仰いだ内閣総理大臣の奏請書である。罫紙の一行目から三行目にかけて上方に「可」の字の朱印が押されているが、言うまでもなく、この可字印は天皇の裁可印である。
山県総理大臣の奏請を受けた明治天皇は、奏請書に添付されている教育勅語の案文を承認し、その徴として可字印を押して、内閣に奏請書を戻したのであった。つまり、この簡単な文面の書類は、総理大臣の裁可奏請書であると同時に天皇の裁可書でもあり、それゆえ奏請・裁可書とよばれるべきものなのである。なお、この書類には「十月二十四日裁可廿五日浄書上奏」と記された付箋が貼られている。この付箋によって明治天皇は10月24日にこの件に裁可を下し、翌25日には浄書された教育勅語の公布原本が天皇のもとに差し出され、それに天皇が親署をくわえたと推測される。ちなみに教育勅語の公布は同年10月30日であった。
この奏請・裁可書とともに教育勅語の制定に関する一件書類が「公文類聚」には綴られているのだが、それを見れば、どのようなプロセスを経て教育勅語が天皇の裁可を受けたのかがよくわかる。まず、明治23年9月26日付で、勅語の案文とその発表の方策を閣議にかけることを求める請求が文部大臣芳川顕正から山県首相になされた。一緒に綴られている文部大臣の閣議請議書がそのことを示している。これを受けた山県内閣は同日の閣議で文部大臣の提案どおりに閣議決定を行ったが、それを示す、総理大臣以下の閣僚の捺印および花押のある閣議書が「公文類聚」の中に含まれている。閣議決定後内閣総理大臣から明治天皇に裁可を仰ぐ奏請がなされ、それに明治天皇が裁可を与えたことを示すのが、前述の可字印の押された奏請・裁可書である。つまり、閣議請求書→閣議書→奏請・裁可書という文書の流れが、意思決定のプロセスを目に見えるかたちで示してくれているのである。
「徳教ニ関スル勅語ノ件」のほかにも、これと同種の奏請・裁可書が国立公文書館のWebサイトには展示されている。次は、同じ内閣文書でも「公文類聚」とは別の文書群である「公文雑纂」に綴られているもので、「陸軍軍医監医学博士森林太郎結婚願ノ件」と題する明治35(1902)年3月6日付の奏請・裁可書(http://www.archives.go.jp/list/kichou_105.html#)である(2)。奏請者は内閣総理大臣伯爵桂太郎で、こちらには「聞」の字の朱印が押されているが、もちろんこれも天皇の裁可印ある。可字印に比べて事柄の軽い案件を決裁する際に、こちらの聞字印が用いられた。表題からわかるように、この書類は森林太郎、すなわち明治の文豪森鴎外と荒木しげとの結婚許可願いに対して明治天皇が裁可を下したものである。今日では信じられないことだが、陸軍武官結婚条例なるものがあって、森鴎外のような陸軍の高級軍人(陸軍軍医監は陸軍少将相当官)は結婚にあたって天皇の許可を必要としたのである。
この鴎外の結婚許可の奏請・裁可書にもやはり一連の文書が附属していて、どのような手続きを経て明治天皇が鴎外の結婚に許可を与えたかがわかる。森?外自筆の「結婚願」は明治35(1902)年2月20日付で内閣総理大臣桂太郎宛に出されており、その「結婚願」の裏に「不都合無之付御許可相成度候也」と児玉源太郎陸軍大臣の添書きが記されている。この?外自筆の「結婚願」に荒木しげの「身元証書」を添えて、結婚の許可を求める児玉陸軍大臣名義の「上奏書」が陸軍大臣から内閣総理大臣に進達され、さらに内閣総理大臣から先に紹介した裁可奏請書が明治天皇に出されて、その奏請書に明治天皇が裁可を下したことによって、?外はめでたくしげ女と結婚することができたわけである(3)。
次に展示されている奏請・裁可書は、物理学者長岡半太郎以下8名に第1回目の文化勲章が授けられた時のもので(http://www.archives.go.jp/list/kichou_106.html#)、昭和12(1937)年4月26日付で、やはり内閣総理大臣林銑十郎が昭和天皇に裁可を仰いでいる(4)。文化勲章の授与は、鴎外の結婚よりははるかに重大な案件であるから、こちらは可字印による決裁である。添付されている一件書類から裁可奏請書が出されるまでの手続きを確認しておくと、まず文部大臣が、内閣総理大臣宛に叙勲の詮議を求める稟申書を提出した(4月23日付)。総理大臣はそれを賞勲局にまわし、賞勲局では議定官の審議にはかったが、議定官は全員一致で叙勲は可であるとの判定を下したので、議定官の議決書をはじめとする一件書類を添えて内閣総理大臣から天皇に叙勲の奏請がなされたのであった。
文化勲章の授与と教育勅語の制定との間には約50年近い年月の隔たりがあるが、国立公文書館の展示文書を見ればわかるように、総理大臣から天皇に差し出された奏請・裁可書の様式はどちらもほとんど同じであり、両者に様式上のおおきな差異を見いだすことはできない。天皇の使用している裁可印についても同様である。内閣の裁可奏請と天皇の決裁を示す文書様式は明治中期に使用されていた形式が、ずっと後までそのまま維持されたことを、これは意味する。
以上、国立公文書館のWebサイトに展示されている奏請・裁可書について説明してきたが、ここで紹介した奏請・裁可書がはたして何を意味するものなのか。すぐわかるように、これらの書類は、国政上重要な案件について天皇が日常的に文書決裁をじきじき行い、内閣総理大臣の奏請に裁可を下していたことを意味している。つまり、これらの奏請・。裁可書は、天皇の「万機親裁」が現実に行われていたことを裏付ける証拠にほかならない。
紹介した、いくつかの例に見られる意思決定の手続きは、おおよそ次のように模式化できよう。
このような国家意思決定のシステムを「万機親裁体制」と呼ぶことにする。「万機」とは「国政上の重要事項のすべて」を意味し、「親裁」は「天皇が自ら裁可を下して、決裁すること」であり、「万機親裁体制」とは「国政上の重要事項すべてについて天皇が最終的決定権をもち、天皇の決裁によってはじめて国家意思が最終的に確定される、そういった国家意思決定システム」と定義できる。上に、模式化した意思決定プロセスは「万機親裁体制」の具体的形態である。もっとも重要な「天皇の決裁」の存在を示す物理的実体が今紹介した奏請・裁可書なのである。
本日の私の報告は、このような「万機親裁体制」が、いったいいつ成立したのかを、歴史的に明らかにすることをめざしている。周知のごとく、慶応3(1867)年12月9日に王政復古の大号令が出され、今後は江戸幕府に代わって「朝廷ニ於テ万機御裁決被遊候」との新政方針が全国に宣言された。さらに翌慶応4(1868)年閏4月22日にはいわゆる「万機親裁の布告」が出され、天皇が「万機之政務被為聞食候」と宣告される。つまり、早くもその成立当初の時点で、天皇の「万機親裁」は新たに樹立された明治政府の最も重要な政治理念として定立されてたのである。ここで定立された政治理念が、以降約80年にわたり、日本の統治体制・政治制度のありかたを大きく拘束しつづけたことは、あらためて指摘するまでもない。
しかしながら、理念の定立とともに「万機親裁体制」が同時に成立したかと言うと、必ずしもそうではない。理念の定立とその現実制度化の間には少なからぬ時間差があり、実際には明治維新後しばらくの間、明治天皇は「万機親裁」などしていなかったのである。「万機親裁体制」と呼びうる制度が成立するのは、明治維新からさらに10年ほどのちの西南戦争後になってからであり、この時間差の存在を実証すること、すなわち理念のほうは早くから定立されていたのに反して、その理念にふさわしい国家意思決定システムはすぐには成立しなかったことを、実証的かつ文書学的に明らかにするのが本報告の第一の目的にほかならない。
それでは具体的にどのようにすれば、「万機親裁体制」の成立時期を知ることができるのだろうか。すでに述べたことから明らかなように、天皇の「万機親裁」は、国立公文書館の電子展示に見られるような奏請・裁可書の存在によって裏付られる。となれば、「万機親裁体制」がいつ成立したのかを知るには、このような奏請・裁可書がいつ登場したのかがわかりさえすれば、それでよいわけである。具体的な方法としては、内閣文書の前身にあたる明治初期の太政官文書を網羅的に検索して、天皇の裁可文書がいつどの時点から登場したのかを調査すればよいということになろう(5)。
以下述べるのは、私自身が行ったそのような調査の結果報告である
太政官正院とは、太政大臣・左大臣・右大臣と参議を構成メンバーとする明治政府の最高政治組織でのちの内閣に相当する。この正院の決裁文書の様式とその変化については、すでに田口慶吉と中野目徹による先行研究があり(6)、文書様式を四段階にわける時期区分はそれらの先行研究にしたがっている。第一期は明治4(1871)年夏の太政官制改革から明治6(1873)年5月の太政官制改革までの約二年たらずだが、なぜ明治初年ではなくて4年からはじまるかと言えば、それ以前の時期については、国立公文書館には太政官の意思決定プロセスを示す文書(原議書)が所蔵されていないためである。
第一期における正院の決裁文書は、図1のような様式をしている。これは明治4年9月29日付の海軍少佐兼兵学大助教田中義門を海軍少佐兼兵学少教授に任ずる人事の決裁書類だが(7)、兵部省から正院にこの上申書が提出され、決裁が下されたことを示すのが、罫紙の右上欄外に押印されている裁字印(朱印)である。この案件は奏任官の任官人事である。
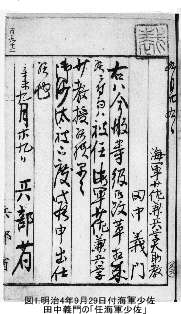
ここで考えるべきは、もちろん、この決裁文書に押印されている裁字印がいったい誰の決裁印なのかという問題である。これについては先行学説が二つに分かれており、ひとつは太政官正院(大臣・参議)の決裁印だとする田口説であり。もうひとつは、これを天皇の決裁印と見る中野目説である。中野目説が正しければ、図1の書類は立派な天皇の裁可書であることになり、すでにこの第一期において天皇の「万機親裁」が行われていたと結論してよい。
逆に田口説が正しければ、まだこの段階では天皇は太政官正院の決定のいちいちについて決裁を下しておらず、いまだ「万機親裁体制」は成立していないとの結論となる。いずれが正しいのか、詳しい検討の過程は省略して(8)、結論だけを言えば、この裁字印は天皇の決裁ではなく正院の決裁を示すものと解釈すべきである。私がそう判断した根拠は、明治4年8月に定められた正院の内規「正院処務順序」に下のように記されているからである。
凡ソ左院ノ法案及各省府県ヨリ上奏スル一切文書ハ外史之ヲ受ケ、其部類ヲ区別シ、番号月日件銘ヲ簿記シ副本ヲ以テ三職ニ呈ス
三職決裁了リ裁印ヲ附シ外史ニ附ス外史之ヲ受ケ本紙ニ批文ヲ記シ捺印シ且ツ其ノ由ヲ簿記シテ後之ヲ其ノ主任ノ官ニ達ス副紙ハ編次シテ之ヲ存ス(9)
各省から上奏される文書は、三職(太政大臣・左右大臣・参議)に提出され、「三職決裁了リ裁印ヲ附シ外史ニ附ス」とあるので、「裁印」は太政官三職の決裁を示すものと解するのが妥当である。
この事実は、太政官正院の意思決定において天皇が親裁を行った形跡を決裁文書の上に見いだすことができない、すなわち当時はまだ天皇の文書による裁可が必須のものとはみなされていなかったことを意味する。言い換えれば、三職すなわち太政官正院の決裁をもって国家意思は基本的に確定し、天皇の裁可を仰ぐ上奏がかりに行われたとしても、それは文書によるものではなく、かつまたその裁可行為が太政官の決裁文書には記録として残されなかったということである。すなわち第一期においては、国家意思の決定プロセスにおいて天皇の親裁は不可欠の項としては定立されておらず、天皇の「万機親裁」はまだ成立していなかったのであった。
ただし、明治4年夏の太政官制改革の時点で、「宸断制可ヲ乞候分正院決裁ノ分トモ両款ノ区別判然致シ不申候テハ権威ノ際限御処置ノ体裁モ宜シカルマシク候」と、天皇の裁可印と正院の決裁印を判然区別すべしとの意見書がすでに提出されていたことが確認できる(10)。つまり、天皇裁可印と正院決裁印とを新たに創るべきであるとの主張がなされており、しかもこの新しい天皇の裁可印の文字としては(「裁」ではなく)、「可」字が適当だとされていた。
この意見書から逆に、当時は天皇の裁可印なるものがそもそも存在すらしていなかったことがわかるが、それとともに、このような正院ないし太政大臣の決裁行為から天皇の裁可行為が独立していない現状は、天皇の「万機親裁」のたてまえにそぐわないとする認識がすでに成立していたこと、さらにそのような現状を改めて、天皇の親裁を名実ともに確立すべしとの主張が打ち出されていたことも、この意見書から判明する。 しかし、太政官文書の正院決裁文書を見る限りでは、そのような要求はただ表明されただけで、実現されないままに終わった。現実には天皇の文書決裁はおこなわれず、明治4年8月の太政官制改革のあとも、「天皇の万機親裁」は制度化されなかったのである。
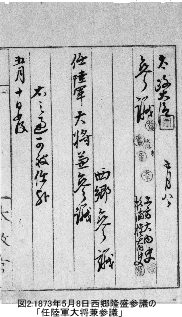
この時期には太政官正院の決裁文書の様式は図2のように変化する。これは、1873(明治6)年5月8日議決、5月10日発令の参議西郷隆盛の「任陸軍大将兼参議」の決裁書類である(11)。罫紙の一行目に「太政大臣」、二行目に「参議」と墨書された押印欄があり、この例では三条実美太政大臣の角印(銘は「実」)と五参議(大隈重信、板垣退助、後藤象二郎、江藤新平、大木喬任)の丸印がはっきりと認められる。筆頭参議西郷の押印がないのは、彼自身の人事だからである。
このような様式の文書は、正院の構成メンバーである大臣・参議の議決を示すものであるので、閣議書あるいは大臣・参議回議書と呼ばれている。第二期にはこの閣議書が正院の決裁をあらわす文書となる。裁印が姿を消し、大臣・参議の押印のある閣議書が新たに登場したところに、第二期の特徴がみられるのである。
このような文書様式の変化は、1873年5月2日の太政官制の改定に由来するものであり、新しく定められた「正院事務章程」において、「正院ハ天皇陛下臨御シテ万機ヲ総判シ、太政大臣左右大臣之ヲ輔弼シ、参議之ヲ議判シテ庶政ヲ奨督スル所」と、参議(内閣議官)の議判権が明確にされたことを反映したものにほかならない。さらに文書の処理法に関する規定を細かくみていくと、「正院事務章程」は上奏書の取扱と参議の議決、太政大臣の決裁及び天皇の裁可の手続きを次のように定めていた。
凡允裁ヲ乞フ奏書ハ内閣議官議判ノ上内史其部類ヲ分チ、之ヲ本帖及ヒ副本ニ写シ、本帖ニハ議官之ニ連印シ、内史之ニ記名シ、之ヲ太政大臣ニ出ス。太政大臣之ニ颸印シ 御批允裁ヲ受ケ之ヲ外史ニ付シテ奉行セシム。但内閣ノ議決スレハ即日本文ノ手続ヲナシ、 御批允裁ヲ経レハ翌日之ヲ頒布スルヲ恒例トス(12)。
允裁すなわち天皇の裁可を仰ぐ奏請書は、まず内閣議官すなわち参議が議判を行い、押印の後太政大臣に提出し、太政大臣が決裁の押印をした後、天皇の御批允裁を受け、そのあと執行にまわすことと定められている。先ほどの西郷参議の人事例では、閣議書に参議の議判を示す押印、内史の記名と押印、太政大臣の颸印と、この規定のすべてをそなえており、天皇の御批允裁を示す表徴がない点を除くと、右の「正院事務章程」に定める手順にそって実際に文書が処理さたことを裏付けている。
このように「正院事務章程」は、正院の決裁ののちに天皇がその案件に御批允裁をおこなうこと、すなわち天皇の裁可が最後になされることを想定していたのであった。しかもその御批允裁は、文書化されること、つまり目に見える表徴として表示されるはずであった。なぜなら「正院事務章程」なる法令の末尾には、左に引用するように、天皇の御批とそれを受けた奉勅の布告文が記されているからである。
御批六年五月二日
右職制事務章程 上裁欽定スル所ナリ
能ク之ヲ守リ其程限ヲ愆ルコト勿レ
奉勅 太政大臣三条実美(13)
さらに「正院事務章程」の制定とほぼ同時に「御批国法允裁」と題する、左のような雛形も定められていた。
「御批国法允裁」 〔太政官罫紙の欄外に「五月七日允裁」と墨書、その下に「三条」と「大隈」の押印あり〕〔朱で抹消〕国法
御批録
第一号
陸海軍官等改定頒布〔朱で抹消〕 布告番号
明治六年五月六日 議定
同年五月八日 奉行
年号月日 連名 印
御批(14)
これらの史料から、1873年5月の太政官制の改定には、正院の決裁と天皇の決裁を分離し、国家意思決定のプロセスの最終項に「御批」すなわち天皇の裁可それも文書による裁可をおくことで、「万機親裁」を実現する意図が内包されていたのだと言わねばなるまい。
ところが、実際には目にみえるかたちでの御批允裁の手続きは実施されないままに終わった。第二期の法令類で「御批」の文字を末尾に有しているのは、上に紹介した1873年5月の「太政官職制及正院事務章程」のみであって、ほかには存在しない。また「御批録」も作られた形跡はない。もちろん、私が網羅的に調査した正院の人事決裁書類を綴録した「諸官進退」にも、天皇の「御批允裁」がなされたことを示す表徴を含む書類はまったく含まれていない。たんに人事案件だけでなく、この時期の太政官正院の決裁文書全体にわたってそれは見あたらない。つまり、文書学的見地からすれば、第二期においても、いまだ「万機親裁」は実現されていない、と言わざるをえない。
「万機親裁」の制度化をめざす意図があったことにまちがいはないが、それは実現されずに終わったのである。なぜ、その意図が制度化されずに挫折したのか。はなはだ興味深い問題だが、それに解答を与えるのは必ずしも容易ではない。ただひとつ言えるのは、少なくとも正院側は「御批允裁」の内規まで定めていたのだから、挫折の原因が求められるとすれば、それは太政官正院の側にではなくて、天皇の側でなければならないということである。
天皇自ら決裁文書に裁可を下すといった、近代的な君主観からすればしごく当たり前と思われる行為であっても、前近代的な伝統的・神聖天皇観にてらせば、天皇たるべき人がなすべき事柄ではないとして、忌避されたのではないだろうか。近代的天皇観と伝統的天皇観とのギャップ、生身の明治天皇の意識と身体が近代的君主としての要請にまだ十分適応できる状態になかったこと(自然年齢や成熟度、君主としての資質、性格、政務に対する姿勢等において)、それが挫折の原因ではなかったかと推測される。
第一期、第二期ともに天皇はいまだ「万機親裁」を行う君主ではなかったというのが以上の考察から導かれる結論であるが、しかしこれはあくまでも、国家意思決定過程である太政官正院の文書決裁システムの流れの中に、天皇の裁可が独立した最終項として組み込まれてはいなかったとの事実をさすのであって、明治天皇が国政上において何らの裁可も下していなかったと主張をするものではない。
太政官文書からわかるのは、正院の決裁文書には天皇の決裁印がないという単純な事実であって、文書に残らない方法で、つまり天皇の裁可を求める上奏が太政大臣によって口頭でなされたり、天皇臨御のもとで御前評議がおこなわれ、そこで正院の議決と天皇の承認が同時になされることまでが否定されたわけでない。この時期には、天皇の裁可は、もっぱら太政大臣の奏聞に対して、天皇が裁可を口頭で与えるか、または御前評議で正院の決定を天皇がその場で承認するか、そのいずれかでおこなわれていたと考えるべきであろう。じっさい『明治天皇紀』には明治天皇が太政大臣の奏聞に裁可を与えたとの記事が多く記載されており、先ほど紹介した西郷隆盛を陸軍大将にする人事などは政府と陸軍の最高級人事であることを考えると、天皇の了解がまったくなしに行われたとは考えにくい。
有名な例としては、明治六年政変すなわち征韓論政変の時の明治天皇の裁定をあげることができる。この時岩倉具視太政大臣代理は、朝鮮への大使派遣の閣議決定をそのまま実行すべきだとする閣議決定の上奏と、岩倉個人の大使派遣反対意見の双方を口頭で奏聞し、その選択を天皇に委ねた。明治天皇は岩倉の上奏を是とする裁定を下し、内閣の内部対立に決着をつけたのであった(15)。
このように、明治天皇は重要な政治的意思決定を自己の裁量によって現実に処理していた。しかし、それはやはり例外的な事件であって、太政官正院が日常的に決裁を下していた重要案件すべてについて必ず裁可を求める奏聞が太政大臣から口頭でなされていたとは想定しがたい。天皇に奏聞されたのは、その中の一部の最重要事項に限られていたのではないかと思われる。また、御前評議で天皇が同時承認をあたえる場合は、意思決定主体としての天皇は、正院と、言わば一体化しており、独立した最終項として機能しているとはみなせない。天皇は国家意思の最終的確定者として独立した主体に、いまだなりえておらず、天皇と太政官正院(とくにその長である太政大臣)は不可分の一体であって、太政官正院の意思決定がただちに天皇の意思でもあったと解すべきなのである。
前章で述べたことに矛盾するように聞こえるかもしれないが、いっぽうでこの第二期には、ごくわずかの例だが、天皇が文書決裁をおこなったことを示す裁可文書がはじめて登場する。その初例が図3である。明治7(1874)年2月28日付の三条太政大臣から明治天皇に出された裁可奏請書であり、罫紙頭部欄外に裁字印が押されている。結文に「断刑ノ儀奉仰御允裁候」とあるように、この奏請書は青木吉五郎以下一六名の死刑判決確定を天皇に求めたもので(16)、「断刑伺」と呼ばれている。
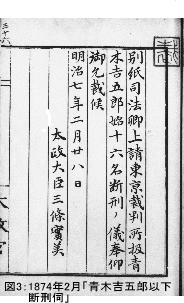
裁判そのものは司法省が管轄する各裁判所で行われ、そこで死刑の判決が出された。しかし量刑が死刑であるために当時の司法制度ではいまだ判決の確定にはいたらず、判決が確定されるためには司法卿が断刑伺を正院に出し、太政大臣から天皇の允裁を仰ぐ必要があった。この太政大臣の奏請書に天皇が裁可印を押すことで、死刑判決が確定したのであった。天皇が司法権を直接に行使していたことを示す文書にほかならない。
太政大臣の奏請書に押されているのだから、この裁字印は、明らかに天皇の裁可印である。つまり、図3の書類は、冒頭に紹介した、明治中期以降の奏請・裁可書と様式において少し違ってはいるが、本質においては同じものと言うべきであって、国立公文書館に所蔵されている天皇裁可書(奏請・裁可書)の初例といってよいものである。その意味でこれははなはだ貴重な文書と言わねばなるない。
この断刑伺の裁字印と第一期の裁字印は文字は同じだが、別印である。図4は図1の裁印(A)と図3の裁印(B)を拡大したものだが、「裁」の字形と外周の枠の形が微妙違うことがわかるであろう。また図4でははっきりしないが、印そのものの大きさが異なっている。第一期の印(A)は方32mmの角印だが、「断刑伺」の奏請・裁可書におされた裁印(B)はこれより一回り小さく、縦26mm、横27mmの大きさである。このことも、第一期の裁字印が天皇印ではないことの傍証となろう。また「断刑伺」の奏請・裁可書は、図2のような通常の太政官正院の決裁文書が、天皇の決裁を受けていないことを逆に証明するものと言える。なぜなら、膨大な正院決裁文書において天皇の裁可印をもつものは、「断刑伺」のようなごく限られた例外にすぎないからである。
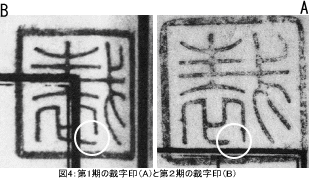
このように、第二期になると、限定的な分野ではあったけれども、天皇による文書決裁のはじまったことが確認できた。しかしながら、この「断刑伺」の奏請・裁可書は長続きしなかった。翌1875年に大審院が設置され、天皇の司法権が大審院以下の裁判所に完全に委任されるにおよんで、天皇による死刑判決の確定そのものが終焉し、それにともなって「断刑伺」そのものが消滅するにいたるからである。
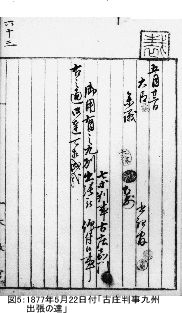
天皇の裁可書が再び登場するのは西南戦争がはじまってしばらくしてからのことであった。その最初の例が図5の書類である。これは1877年5月22日付の七等判事古荘嘉門に九州出張を命じた辞令の原議書であるが(17)、太政大臣(三条)、参議(大久保利通、伊藤博文、大木喬任)の議判のあと欄外に裁印がおされている。すでに大臣・参議の花押・印判があることから、この裁印は大臣・参議のものではありえない。さらに印の大きさと字形が「断刑伺」の天皇裁印と同じあることから、この裁印は天皇印と断定できる。 第二期における正院の決裁文書様式である大臣・参議の閣議書の欄外に裁印が押されているので、図5の様式の書類は、閣議書が同時に裁可書でもある天皇裁可閣議書とよぶことができよう。ここではじめて、通常の正院の決裁文書に天皇が裁可印を押すことがはじまったわけである。閣議書に天皇の裁印が直接押印されている点で、この文書は従来にない様式のものと言わねばならない。「断刑伺」は太政大臣の奏請書に裁印が押されたのであって、それ自体は閣議書ではなかった。この文書の登場により、太政官正院の決裁後さらに天皇が御批允裁を下すという1873年の太政官制改革の際に想定されていた状態がはじめて実現されたのであった。これは西南戦争中に明治天皇が京都に滞在していた時のことである。
なぜ、この時に突然天皇の文書決裁が日常的におこなわれるようになったのか、その理由は定かではない。明治天皇が大きく変身したらしいことはまちがいないが、当時の京都太政官はもっぱら戦争にかかわる政務・軍機を処理しており、最高戦争指導部の機能を果たしていた(一般の政務は東京で留守を守っていた岩倉右大臣以下の留守太政官が処理していた)。つまり、明治天皇が日常的に太政官正院の文書に決裁を下すようになったのは西南戦争の戦争指導においてであったのである。言い換えれば、明治天皇は京都の最高戦争指導部の中にあって「万機親裁」を開始したのであった。
西南戦争の帰趨がはっきりすると、明治天皇は京都から東京に戻るが、還幸直後の1877年9月初めに太政官内閣(正院の呼称は廃止され、内閣とよばれるようになった)の決裁文書の様式はもう一度大きく変化することになる。図6がその新しい様式のもっとも早い例で、明治10(1877)年9月6日付決裁の、鹿児島県士族福崎季連を霧島神宮大宮司に任じる人事案件文書である(18)。
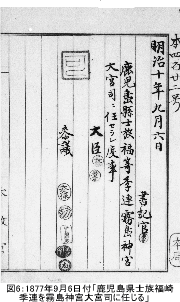
図からわかるように、太政官の内閣書記官が起草した閣議書に、大臣(三条と岩倉)・参議(大久保、大木、寺島宗則、伊藤、黒田清隆)が押印し(閣議議決)、さらに天皇が裁可印を加判して、決裁が行われたのであった。閣議書が同時に裁可書でもある点では西南戦争中の天皇決裁文書と同じだが、天皇の裁可印が欄外にではなくて、最初から罫紙の中央部に区画された押印欄に大臣・参議の印の上に押印されている点にちがいがある。また、この時期になってはじめて天皇の裁可印には裁字印ではなく、可字印が用いられるようになる。
また、西南戦争中はもっぱら戦争指導に関わる事柄に限られていたのだが、第三期に入ると太政官内閣の重要決裁文書のほぼすべてに天皇の裁可印が押されるようになる。その点でも第一期、第二期とはちがうのである。西南戦争中に現れた天皇の文書決裁が恒常化し、文字どおり天皇が万機を親裁する体制がようやくここに出現したのだと言えよう。維新後10年を経て「天皇の万機親裁」理念に応じた文書決裁様式が出現したであり、近代天皇制の歴史において画期的な事件と言わねばなるまい。
この新たな様式を法的に規定し、制度化したのは、1877年9月7日付で大臣・参議が連署上奏し、天皇の裁可を受けた「内閣参朝公文奏上程式」であった。
一、毎朝第十時暑中ハ第九時内閣ニ 臨御大臣参議ハ 臨御ノ前参朝
一、内閣枢機ノ事務ニ係ル会議ヲ行フハ必ス 臨御ノ時ニ於テス
一、内閣ノ公文分テ二類トス
其一 親裁ヲ仰ク者
其二 奏事旨ヲ取ル者
一、凡ソ重大ノ事欵 親裁ヲ仰ク者ハ其裁可スルノ可印ヲ親颸シ付下ス其可セサルハ 旨ヲ以テ大臣参議ニ下ス
一、凡ソ奏事 旨ヲ取ル者ハ其奏ニ依ルノ聞印ヲ 親颸シ付下ス其奏ニ依ラサルハ 旨ヲ以テ大臣参議ニ下ス
一、凡ソ事変災異消息ノ類 御覧ニ供フルニ止マル者ハ 覧終テ覧印ヲ颸ス(中略)
一、凡ソ公文ノ裁若クハ聞ヲ請フ者ハ大臣参議案ヲ奉ケテ上進シ其大意ヲ奏陳ス其急速ヲ要スル者ハ併セテ其事由ヲ奏ス
一、文書ノ繁簡ト事欵ノ緩急ニ従ヒ中ニ留メ 覧ヲ経次日若クハ後次日内閣ニ於テ 親ク大臣参議ニ付下ス其ノ中ニ留メテ久ク下サヽルアレハ大臣参議便奏シテ 旨ヲ乞フ
(略)(19)
右の引用からわかるように、「内閣参朝公文奏上程式」とは天皇の内閣臨御および天皇の文書決裁の手続きと奏請・裁可文書の様式を定めた内規にほかならない。天皇は毎日午前10時に内閣に臨御し、その臨席のもとで重要案件を議定するとされ、さらに天皇が決裁すべき内閣の公文書を二種類にわけ、重大事は「可印ヲ親颸」し、より軽事である「奏事旨ヲ取ル者」は、「聞印ヲ親颸」して内閣に下付し、さらにただたんに御覧に供するのみで裁可を要しない案件は、「覧印」を捺して返却すると定められている。軽重いずれにしろ天皇の裁可・承認を仰ぐ公文書は、大臣・参議が上進して、説明を行い、天皇は次の日またはその次の日に裁可書を大臣・参議に下げわたすのであった。内閣の公文書の重要なものほぼすべてに天皇の裁可印が必要であるとの原則が、ここではじめて定立されたわけである。
この時の文書式の様式と決裁方式の改革の目的が「万機親裁」理念にふさわしい文書決裁システムを確立するところにあったことは、「内閣参朝公文奏上程式」の奏請文に、「明治十年八月十五日太政官ヲ宮中に移サレ日々ニ 臨御万機ヲ総攬シ 親裁ノ実ヲ挙ケ且ツ文書ヲ批閲シ国事民情ヲ訪察シ以テ中興ノ治ヲ拡張シ玉ハントノ 聖旨ヲ奉シ」て、この内規を定めたと説明されていることから明らかであろう。まさに「日々内閣に臨御し、万機を総覧、親裁する天皇」にふさわしい文書決裁システムとしてこの公文奏上程式が定められたのであった。文書学的見地からすれば、この時すなわち1877年9月初旬をもって「万機親裁体制」が始まったと言うべきなのである。
以上のような文書式の改革と並行して、宮内省に侍補が設置された(20)。侍補は天皇の側近に仕えて、天皇を導き、補佐すること、すなわち君徳輔導をその任務としたが、この侍補の設置と「内閣参朝公文奏上程式」の制定とは密接な関係にあり、両者は同じひとつの動きの異なった側面と解される。なぜなら、「内閣に日々親臨し、万機を親裁する天皇」が現実に機能することになれば、その側近にあって常時天皇を補佐し、正しく導く者が不可欠であるとの認識が生まれてくるのは、半ば必然的だと言えるからである。
さらに言えば、ひとたび天皇が実際に万機を親裁し始めれば、天皇はたんなる「神聖なる捺印機関」であってはならず、内閣の政治にその個人的意思が正確に反映されて然るべきだとする考え方や、宗教的に神聖であるばかりでなく、国民道徳の源泉として倫理的主体でもあるべき天皇が万機を親裁するのだから、内閣の政治は天皇の君徳を傷つけるものであっては決してならない、閣臣もそれにふさわしい徳をそなえた立派な人物を選ぶべきだとする考え方、そして少しでも内閣の政治が天皇の名にふさわしい理想政治に近づくよう、侍補たる者はたえず政府を監視しなければならないとする考え方が、そこに生じたとしても少しも不思議ではない。
西南戦争後から1879年にかけて侍補の「天皇親政運動」なるものが展開されたことはよく知られているが、この「天皇親政運動」はまさに、いま指摘したような考え方に立脚していた。西南戦争後にはじめて「万機親裁体制」が出現した事実は、なぜこの時期に侍補が置かれ、なぜこの時期に「天皇親政運動」なるものが発生したのか、その背景をよく説明してくれるであろう。
第三期のもうひとつの特徴は、内閣の奏請によらない天皇の裁可書が登場する点に求められる。図7がその原本の初例である。これは1879年1月6日付の野津道貫陸軍少将の近衛参謀長御用取扱を免ずる奏請・裁可書である(21)。
図7からわかるように、この文書は閣議書ではない。大臣・参議の押印はみとめられない。また、結文に「左之通奉允裁候也」とあるように、天皇に裁可を求める奏請書の形式をとっている。奏請者は陸軍卿西郷従道と参謀本部長山県有朋の二人であり、その官職はいずれも太政官内閣のメンバーではない(西郷と山県はともに参議を兼任しており、参議としては内閣の一員である)。この奏請書は閣議および太政大臣を経由せずに参謀本部長から天皇に直接上奏され、天皇の裁可をうけたあと、その執行(人事発令)のために内閣に下付されたものである。このような軍部からの直接の奏請書が帷幄上奏書であり、それが新たに登場してくるところに、それ以前には見られない第三期のもうひとつの特徴が見られる。
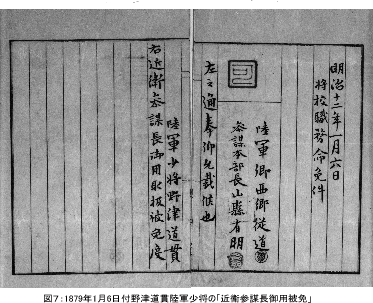
太政官制においては、天皇に対してこのような裁可を仰ぐ奏請を行うことができるのは、太政大臣または左右大臣に限られていた。大臣ではない参謀本部長と陸軍卿が天皇に対してこのような奏請を直接行うことがなぜできたのか。
参謀本部長に対して帷幄上奏権(太政大臣を経由しない直接上奏権)を与えることを認めた参謀本部条例(1878年12月)にあげられているのは、「軍中ノ機務、戦略上ノ動静、進軍駐軍転軍ノ令、行軍路程ノ規、運輸ノ方法、軍隊ノ発差等其ノ軍令ニ関スル者」であって、右のような将官に職務を命じあるいは免じることは含まれていない。ただ、参謀本部条例制定の際に、同時に設けられた内規「本省ト本部ト権限ノ大略」に「然レトモ将校ノ職務ヲ命シ、或ハ之ヲ免スル等ノ事ニ於テハ、陸軍卿、本部長ニ移シテ上裁ヲ乞ハシム」という条項があるので(22)、法的な根拠を求めるとすればこの内規以外にはない。
それまでは、陸軍の将官クラスに職務を課す場合には、陸軍卿が太政大臣に上申し、内閣の議決を経て天皇の裁可を受けていた。そのことは、私が悉皆調査した太政官の人事決裁文書から明らかである。天皇に裁可を仰ぐ上奏権は内閣(太政大臣)にあったのだが、参謀本部が設置されて以降は、参謀本部長と陸軍卿のような帷幄機関、すなわち軍部が奏請権の保持者となり、陸軍の将官に職務を課す権限は内閣の手を離れ、天皇とその帷幄(=幕僚)によって、内閣からは独立して決定されることになった。これが人事面からみた統帥権の独立のはじまりにほかならない。
またここで注意すべきは、参謀本部長にとどまらず、陸軍卿も帷握上奏権を行使している点である。元来は内閣に下属する行政長官にすぎない各省卿は、天皇に対して直接裁可を仰ぐ上奏権をもたなかった。必ず内閣を経由して太政大臣が奏請したのである。ところが統帥権の独立が認められると、陸軍卿は他の省卿がもたない直接奏請権なる特権を行使できるようになった。これが軍部大臣の帷幄上奏権の起源にほかならない。ちなみに、図7は、原本が現在も残っている帷幄上奏書の中でもっとも古いものである。
西南戦争後に登場した「内閣に親臨し、万機を親裁する」天皇は、その一年数ヶ月後には、太政大臣・内閣の輔弼によらずに、もっぱら参謀本部長と陸軍卿の輔翼によって陸軍の軍務に決裁を与える存在に進化した。この第三期には、天皇と太政大臣・内閣の関係が二度大きく変化したと言える。一度目には1877年9月からはじまった「万機親裁」により、太政大臣・内閣と天皇の一体・不可分性が清算され、天皇は、太政大臣の輔弼を受けつつも、国家意思確定の最終項として自らを自立させた。二度目は1878年末から帷幄上奏事項を親裁しはじめたことで、太政大臣の輔弼によらずに、内閣とは独立して統帥権を行使する大元帥となったのである。
ここで興味深いのは次の点であろう。たしかに帷幄上奏書は第三期に出現した内閣の閣議・裁可書とは文書様式が異なるが、しかし、どちらも天皇の裁可書である点で共通している。このことは何を意味するか。先に内閣の上奏について天皇の文書決裁が制度化されていたからこそ、帷幄上奏書が出現可能となったのである。言葉を換えて言えば、内閣の決議と天皇の裁可とが分離し、天皇の決裁が国家意思確定の最後の項として独立していたからこそ、内閣とは異なる軍部の奏請を天皇が裁可することが可能になったのである。つまり、統帥権の独立が成立するためには、その前提として天皇の裁可行為が内閣の意思決定行為から分離・独立していなければならず、天皇の「万機親裁」が先行的に確立されていなければ、統帥権の独立そのものがありえないということを、これは意味している。
統帥権の独立に関しては、昔から、なぜ1878年末という時期にそれが成立したのか、ながらく問題とされてきた。しかし以上の考察からすると、第一期や第二期には統帥権の独立がそもそも不可能であったことが自然に納得される。なぜなら、統帥権独立の前提条件である「天皇裁可の内閣からの独立」つまり天皇の「万機親裁」そのものが、1877年9月にはじめて実現したのであるから、それ以前には統帥権の独立そのものがそもそも不可能であったと言わざるをえない(23)。
天皇の裁可が太政官内閣の決裁と分離せず、未分化である間は、国家意思の最高最終決定権は天皇と一体化した太政官内閣にあり、その状態のままでは軍部が太政官内閣の議決を仰がずに、太政官内閣に対して効力をもちうる決定をおこなうことは原理的に不可能である。繰り返して言えば、まず前提として天皇の「万機親裁」が制度的に確立されていなければ、帷幄上奏も統帥権の独立も原理的に成立不可能だということである。
第三期になって新たに出現した「万機を親裁する天皇」の登場は、天皇側近に侍る侍補をして「天皇親政運動」におもむかせたが、同様に、「天皇の軍隊」であることを自らの建軍理念としてきた軍部の中に、「天皇の軍隊親率」を制度的にも確立しようとする気運を生んだとしても、不思議ではない。参謀本部の創設は天皇の「万機親裁」の開始によって出現した「天皇の親政」をめぐる政治状況への軍部とくに陸軍の反応といってよく、その意味では陸軍の「天皇親政運動」の産物と見なされるべきものなのである。
第四期になって、太政官の決裁文書式はさらにもう一度変化する。図8と図9がその一例である。これは陸軍中将山県有朋の近衛都督を免じ、新たに陸軍中将鳥尾小弥太を近衛都督に任じる人事の決裁書類である(24)。
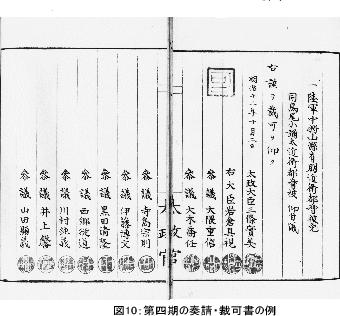
図8:第四期の奏請・裁可書の例
図8が奏請・裁可書であり大臣・参議の連署した奏請書に天皇の可印が押されている。いっぽう、図9はその人事案件を議決した内閣の閣議書である。奏請・裁可書に署名している大臣、参議の花押と押印が認められる。第三期には内閣の閣議書と天皇の裁可書が一枚の同じ書類であったのが、第四期になって閣議書と奏請書が実体として分離し、天皇の裁可は閣議書ではなくて、大臣・参議の連署奏請書に下されるように変化した。第四期になってあらたに登場したこの大臣・参議連署の奏請・裁可書は、冒頭で言及した教育勅語制定の際の内閣総理大臣の奏請・裁可書の前身にほかならない。この奏請・裁可書こそが天皇の「万機親裁」を裏付ける文書にほかならないから、この第四期に「万機親裁体制」が名実ともに確立したといってよいわけである。

図9:第四期の閣議書および辞令案の例
第四期の文書式を定めた内規が、1879年4月7日「御前議事式及公文上奏式施行順序附公文回議手続」であった(25)。この内規は、天皇の裁可を仰ぐための奏請書の書式を四種類に分類し、その最初に大臣・参議が詔勅施行の裁可を請う覆奏式を定め、次に三種類の奏事式を規定している。図8の大臣・参議連署の奏請書は、この第一類奏事式にのっとったもので、大臣・参議が連署して、結文には「右謹テ裁可ヲ請フ」と記し、天皇が可印を用いて裁可を下すと定められている(ただし、図8では「裁可ヲ仰ク」と変更されている)。これに属する事項として、法律の制定・改正、太政官や各省の職制・章程の制定・改正、予算の出納、税率の変更、国債の発行とその償却法、貨幣の鋳造・紙幣の増減、大きな工作、奏任(以上の)官位、特赦、国郡の経界変更などがあげられている。
次いで「恒例アル者及ヒ小事ニシテ内閣ノ議定ヲ要セサル者」が第二類の奏事とされ、こちらは閣議の決定を要さず太政大臣および左右大臣より直ちに奏聞すべしとされている。結文には「右謹テ奏ス」が用いられる。天皇の裁可印は聞印が用いられる。最後に第三類奏事は裁可を仰ぐのではなく、たんに天皇に報告するだけでよいもので、内閣書記官より宮内卿を経由して上呈されるにとどまる。書式は太政大臣・左右大臣の連署上奏、結文は「右謹テ御覧ヲ仰ク」で、天皇印は「覧」印である。
奏請・裁可書が閣議書から分離・独立したことにより、内閣の議定の書式(回議書式)も別に様式が定められた。それが「附公文回議手続」であるが、図9の閣議書はその実例である。新しい書式の閣議書には大臣と参議のみが押印し、それゆえ閣議書の書式としては第二期のそれに回帰したように見える。しかし、この閣議書は、奏請・裁可書が次に存在することを前提とするものである点で、第二期の閣議書とは性格がまったく異なる。
ここにいたって天皇決裁と太政官内閣決裁の分離が完成した。このことは、天皇の太政官内閣からの独立が文書様式の上で、名実ともに確立されたことを意味する。この決裁文書の様式は、「万機親裁」を示す文書様式として以後定着し、1885年の内閣制移行後もそのまま踏襲され、その基本的骨格において大きな変更なしに、昭和期にまで及んだ。そのことは、国立公文書館の展示の説明から納得されるであろう。この第四期様式の出現により、文書学的には天皇の「万機親裁」制度的にかたまったと結論できる。
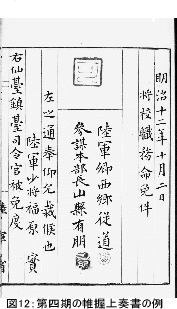
図11:1943年の帷握上奏書の例(下)
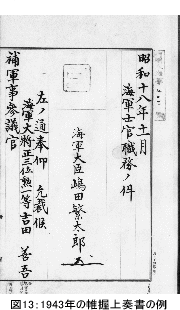
図10:第四期の帷握上奏書の例(上)
同時に指摘しておかねばならないのは、この1879年の文書式改定は、内閣からの奏請書に限られ、帷幄上奏書には及ばなかったという事実である。これ以降、内閣からの奏請はすべて新しい書式にしたがった奏請。裁可書が使用されるが、帷幄上奏書の書式は第三期後半の様式をそのまま保ったままであった。そのことを示すのが図10である。これは明治12(1879)年10月2日の日付をもつ陸軍少将福原実の仙台鎮台司令官を免ずる人事であるが(26)、文書様式は図7の帷握上奏書(第三期)とまったく同じである。さらに言えば、帷幄上奏書は、それが出現してから65年たってもほどんど書式に変化がなかった。そのことを示すのが図11である。これは昭和18(1943)年11月の日付をもつ海軍大将吉田善吾を軍事参議官に任命した際の帷幄上奏書である(27)。奏請者が海軍大臣のみになっている点を除き、図7、図10とほどんど同じ様式である点に注意してほしい。
以上述べたことから、「万機親裁体制」は西南戦争後の1877年9月の改革にはじまり、1879年4月の改革で確立したことが理解されるであろう。ここで確立された国家意思決定のシステムが、細部は時期に応じて変化しつつも、基本的な骨格においてそのまま第二次大戦の終わりまで継続したことは、冒頭で述べたとおりである。と同時に、1879年の文書式の改定の適用範囲が内閣上奏に限定され、帷幄上奏には及ばなかった事実は、この時の改革そのものが、それが適用されない天皇の決裁行為が別個に存在することを、暗黙の前提においてなされたものであったことを裏から証明している。統帥権の独立を暗黙の前提としていた点で、1879年の改革は、その直接の起源となった1877年のそれとは異なるものであった。
1879年4月以降、天皇は文書様式からして明確に異なる二種類の奏請を受取り、そのいずれにも決裁を下す存在となる。たんに「万機親裁体制」が確立されただけではなくて、その「万機親裁体制」が内閣と軍部の双方の領域にまたがるものであったこと、言い換えれば、内閣と軍部の両方に屹立し、万機を親裁する天皇というものが、同時に確立されたのであった。天皇に対してその裁可を仰ぐ奏請権を持つ者を天皇の輔弼者と定義するならば、「万機親裁体制」はそれが確立された時点で、内閣と軍部の二つの輔弼者をもつ二元的輔弼制をとったと結論できよう。
1885年末に太政官制が廃止され内閣制度に移行すると、宮内省が内閣から分離し(宮中と府中の分離)、宮内大臣は独立した輔弼者となる。天皇大権を三つの領野(国務大権・統帥大権・皇室大権)に分割して、それぞれに別個の輔弼者(内閣・統帥府・宮内省)をたてる多元的輔弼制が成立したのである。その点において「万機親裁体制」は、太政官正院による一元的輔弼制を本質としていた1877年9月以前の太政官制(とそのもとでの天皇と太政官正院の一体性)とは根本的に異なる体制と言わねばならない。
この多元的輔弼制をとる「万機親裁体制」こそが、近代天皇制の国家意思決定システムの核心であり、その後の体制の土台となった。明治憲法が制定されても、この土台はそのまま残り、いや、明治憲法に規定される立憲君主制は、むしろこの土台のうえに築かれたのである。多元的輔弼制に立つ「万機親裁体制」を核にして、それを包むかたちで明治立憲君主制が成立したのだと解すべきなのである。
最後に、近代天皇制の統治体制について私なりの考えを仮説として提示しておきたい。私は近代の天皇制(あるいは天皇の地位)は次のような三層構造をもっていると考える。また、この三層構造ができあがるのは、1890年の明治憲法の成立とその後の定着の過程であったと考えている。
いちばんの最下層の核をなす部分は、前近代(直接的には江戸時代)の天皇の存在形態を継承する部分である。ここでの天皇は、「神」または「神の子孫」として聖別された存在であり、また宮中の祭祀を司る「祭祀王」であることを本質としている。
古代末期に摂政・関白や「治天の君」(=院)の登場により「祭と政」の機能が分離し、天皇は専ら「祭祀」を受け持つ宗教的存在として純化しはじめる。現実の政権は関白や院が握り、さらにそれは武家=将軍の手に移っていった。江戸時代には朝廷そのものが政権とは無関係の存在となるが、朝廷内での天皇と関白の機能分化は従前どおり継承されていた。朝廷の日常的な運営は関白とその下の役人が担当し、天皇は関白から奏聞を受け、その輔弼にしたがって祭祀と政務を遂行していた。しかも、江戸時代には天皇・関白が扱うことのできた政治権限そのものがきわめて限定的だったのである。
政治権力的には天皇はゼロに等しい存在であり、それゆえに政治的には、関白と天皇は一体であった。ここにおいて天皇は二重の意味で受動的な君主だったとみなせる。すなわち、朝廷内においては関白の輔弼に受動的したがう存在であり、しかも政権を握る幕府によって名目的に推戴される存在であった点、で。
明治維新の王政復古によりこの状況は打破された。幕府に代わって朝廷が政権を掌握したからである。天皇は祭祀王にとどまらず、政治的君主として復権し、古代のごとく親政を行う存在であると宣言された。また、関白は廃止され太政大臣が置かれた。
しかし、太政大臣は天皇の最高の輔弼者であり、天皇と太政大臣の関係は、前近代すなわち江戸時代の天皇と関白の関係と比べて、それほど大きな変化は生じなかった。「天皇=祭祀王」、「太政大臣(関白)=政権の運用者」という関係は即座に解消されるものではなかった。
太政大臣の管掌する範囲は天皇の大権のすべてにわたっており、しかも太政大臣は天皇に裁可を求めることはあっても、それは口頭でおこなわれ、天皇の裁可が国家意思を成立させるに必要不可欠のものとはなっていなかった。このような状況では「天皇親政」とは言い難い。あるいは天皇の親政はまったくの名目にすぎなかったと言ってもよい。
その点に着目すれば、1877年までは、基本的に前近代的な天皇のあり方がそのまま継続していたといえよう。表面は天皇親政だが、実質は祭祀王である天皇を太政大臣が一元的に輔弼するという形態が維持されたのである。ただし、天皇のあり方に大きな変化を求めるベクトルは常にはたらいていた。つまり、天皇親政を実質化することを望む声が大きな力としてたえず機能していたのである。
この段階では、まだ憲法は成立していないから、もちろん、この体制を立憲君主制とよぶことはできない。天皇は専制君主であった。しかし、この専制天皇は、太政大臣に実質的に政権を委任した受動的君主である。すなわち、専制君主制であっても、君主が受動的である例が実在するのであり、太政官制の下での初期の天皇はその一例であった。
それが1877年から1879年の間に大きく変化した。太政大臣と天皇の関係が変化し、太政官内閣の重要決定のすべてについて、天皇が最終的国家意思決定者として裁可する制度がうち立てられ、天皇が実際に万機を親裁しはじめたのである。太政大臣=内閣の輔弼を受けつつも、天皇が独立の裁可主体として国家意思決定過程の最終項として自立した。これによって王政復古以来のスローガンである「天皇親政」に実(=「万機親裁体制」)がともなったのである。もはやこの天皇は前近代的な天皇とは切れている。
前近代的な天皇との断絶は、万機親裁体制の成立が統帥権の独立とほぼ同時に、それを内に含むものとして成立した点にも求められる。それまでの太政大臣の輔弼は、かつての関白のそれがそうであったように、天皇の統治権のすべてに及んでいた。しかし、統帥権の独立を内に含む万機親裁体制にあっては、太政大臣およびその後継者である内閣総理大臣の輔弼の範囲は天皇の大権すべてには及ばず、いわゆる「国務」だけに限定された。それまでの太政大臣と太政官内閣による一元的輔弼制が内閣と軍部による多元的輔弼制に変化したのである。
天皇は互いに独立する複数の輔弼者の上に立って決裁を下す存在となった。これを多元的輔弼構造をとる「万機親裁体制」とよぶ。これが前近代とは区別される新しい天皇制の第二の層を形成する。しかし、その下層に「祭祀王」的天皇が強力に把持され続けたことを忘れてはならない。これによって天皇は、宗教的に聖なる存在にして、なおかつ政治的にも至高の存在であるというヨーロッパの君主には見られない特性を帯びることになった。[また、伝統的な祭祀に加えて、近代になると国家的な儀式、祭典、式典を主宰することが、天皇の重要な職務となる。象徴的行為の中心に身を置くことで、国家統合のシンボルとなることが新たに機能として加わったのである。]
また、万機親裁体制の下でも、天皇が基本的に「受動的君主」でありつづけた点において、前近代的な天皇の性格の一面がなおも保持されたと言える。天皇は輔弼者の奏請をまって、それを裁可するというかたちでその大権を行使するのであって、通常は自発的にイニシャティブをとらないといった、君主の行動パターンの伝統は残った。
そのかわりに、あるいはそれゆえにこそと言ってよいかもしれないが、「多元的輔弼制」がとられたのであった。一元的輔弼制のもとでは、君主の大権を一元的に輔弼する臣下に実質的な政治権力が移動する危険性を常にはらんでいるが、多元的輔弼制は、君主大権を分割し、そのそれぞれについて異なる輔弼者をたてることで、臣下の権限の強大化と集中を防止することができるからである。
明治憲法と皇室典範の制定により、このうえに次の第三層がかぶさる。多元的輔弼制を特徴とする「万機親裁体制」を基盤に明治立憲制が形成されるのである。多元的輔弼制は国務・軍務・宮務の三領域に内閣・軍部・宮中の三輔弼者が並立するものとして立憲制を支える骨格を形成した。輔弼者に対する天皇の関係は基本的には受動的である。しかし、同時に多元的輔弼制は輔弼機関間の意志が対立した時の最終的裁決者という機能を天皇に課さずにはおかない。ここに、天皇が能動的君主として実質的親政を行わなければいけない制度的必然性が生じる。
立憲制の導入によってもたらされた大きな変化は、有権者によって選出される衆議院に法律制定への協賛権と予算審議の権限を与えたこと、および国民の権利義務を定め、その変更はかならず法律によらねばならぬとしたことである。
当初の構想では強大な君主権を保証するために、ドイツ型の立憲君主制がモデルとされた。しかし、ひとたび議会に権限が付与されれば、内閣が議会の掣肘を受けずにはすまない。憲法の制定が政党内閣の出現を経て、イギリス型議院内閣制への接近をもたらすのは、ある意味で必然の動きであった。
明治憲法によって付加された三層目において、ドイツ型立憲君主制からイギリス型立憲君主制へという、移行の動きが現実に生じたことは否定できない。この接近を促進した日本的要因としては、二層目の「万機親裁体制」における天皇のあり方が基本的に受動的君主であったこと。それゆえ首相権限の弱いドイツ型(多元的輔弼制をとる)ではなくて、首相権限のより強いイギリス型(一元的輔弼制をとる)に移行しやすい力学がはたらいたとみなせる。
しかし、三層目の変化は二層目の「万機親裁体制」を完全に変革するまでの深度はなかった。多元的輔弼構造の解消にはいたらずに終わるのである。つまり、日本の立憲君主制はイギリス型の立憲君主制に接近はしたが、しかしイギリス型の立憲君主制に転化することはなかった。日本の立憲君主制は多元的輔弼構造をとる「万機親裁体制」を保持したまま、それを変改することはなかったのである。
(1)「徳教ニ関スル勅語ヲ宣布セラル」『公文類聚』明治二十三年第一四編一政体門(国立公文書館所蔵)、簿冊番号は2A--11類448(以下同様)。なお、「公文類聚」とは、1886年以降の内閣の公文書群全体に与えられた名称である。
(2)「陸軍軍医医学博士森林太郎結婚願」『公文雑纂』明治廿五年、陸軍省一、巻五四(国立公文書館所蔵)、2A-13纂640。
(3)明治天皇の裁可後、内閣から結婚勅許の指令が下された。それを示すのが「願ノ通裁可ヲ経タリ」との指令を定めた「陸軍軍医監医学博士森林太郎結婚願ノ件」と題する内閣総理大臣の決裁書である(前掲「陸軍軍医医学博士森林太郎結婚願」)。
(4)「長岡半太郎外八名文化勲章授与ノ件」『叙勲裁可書』昭和十二年、叙勲巻三、内国人三(国立公文書館所蔵)、2A-18勲798。
(5)実際に私が悉皆調査を行ったのは、国立公文書館に所蔵されている明治期の太政官文書のすべてではなくて、その一部にとどまる。具体的には「諸官進退」と名付けられた公文書群であるが、これは明治4年7月から明治12年12月までの官吏の任免などの人事案件に関連する太政官文書を年月日順に編集したものである。ただし、人事案件といっても文書の様式そのものは他の太政官文書と同じであり、これを見るだけでこの時期の太政官文書の様式変化を正確に知ることができる。
(6)田口慶吉「近代太政官文書の様式について」『北の丸』19、1987年、中野目徹「明治十二年の太政官官制改革」『日本歴史』586、1997年(中野目『近代史料学の射程―明治太政官文書研究序説―』弘文堂、2000年所収)。
(7)『諸官進退状』辛未三秋第一(国立公文書館所蔵)、2A-18任A1。
(8)田口説と中野目説の検討についての詳細は、永井和「太政官文書にみる天皇万機親裁の成立」『京都大学文学部研究紀要』41、2002年を参照されたい。なお、同論文は永井和のWebサイトからPDFファイルの形式でダウンロード可能である(http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/%7Eknagai/personal/chosaku.html)
(9)「正院処務順序」内閣記録局編 『法規分類大全』第一編、官職門一至六、156頁。
(10)『法規分類大全』第一編、政体門三、141頁。
(11)『諸官進退状』癸酉五月同六月第一四(国立公文書館所蔵)、2A-18任A14。
(12)「太政官職制並正院事務章程」『法規分類大全』第一編、官職門一至六、162。
(13)右同書、164頁。
(14)『官符原案』第六、自明治六年五月至同年十二月(国立公文書館所蔵)、2A-33-5単216。
(15)宮内省編『明治天皇紀』第三、吉川弘文館、1969年、146‐150頁。
(16)「青木吉五郎始断刑伺」『公文録』明治七年三月、司法省伺、二(国立公文書館所蔵)、2A-9公1229。「断刑伺」に対する天皇の裁可が奏請・裁可書形式をとるようになったのは、1874年2月5日の正院の決定「断刑伺書ニ御裁印押捺雛形ヲ定ム」(『公文録』明治七年二月、宮内省之部、全、一五、2A-9公1249)に基づいている。それ以前の「断刑伺」の決裁は、司法省から正院に上申された断刑伺書に正院が裁印を押して司法省に下付することでなされていた。判決確定に対する天皇の裁可は、太政大臣から文書による奏聞依頼が宮内卿に対してなされ、宮内卿が口頭で天皇の裁可を仰ぎ、それを書面で太政大臣に伝えるとの宣旨方式でおこなわれていたと思われる。
(17)『明治十年行在所公文録』一、本局之部、六三(国立公文書館所蔵)、2A-10公2160
(18)『諸官進退』明治十年九月、2A-18任A60
(19)『官符原案』明治十年自七月至一二月、第十三、2A-33-5単223。
(20)『明治天皇紀』第四、245頁。なお、侍補の「天皇親政運動」については、笠原英彦『天皇親政』中公新書、1995年が詳しい。
(21)『諸官進退』明治十二年一月、2A-18任A67。
(22)『公文録』明治十一年十一月十二月、局伺一、2A-10公2247。『法規分類大全』第一編、兵制門二、陸海軍官制二、425頁。
(23)「万機親裁体制」の成立と統帥権独立の時期についての関係については、前掲拙稿「太政官文書にみる天皇万機親裁の成立」を参照されたい。
(24)『諸官進退』明治十二年九月十月、2A-18任A73
(25)『公文録』明治十二年、官符原案、全、2A-9公2616。『法規分類大全』第一編、政体門三、詔勅式、132、133頁。
(26)『諸官進退』明治十二年九月十月、2A-18任A73。
(27)『任免』昭和十八年十二月、巻二六四(国立公文書館所蔵)、2A-18任B3571。